見た目の3段鍵盤の迫力もさることながら、その出せる音色の種類の豊富さ、優秀さもしっかり兼ね備えた楽器。それが電子オルガンです。
そうすると、せっかく電子オルガンで作曲をするのなら、その性能・機能をがっちり使って魅力を表現したい、と思ってしまうのが作曲家・プレーヤーの性です。
しかしながら、その溢れ出す魅力に溺れてしまい、結局中途半端な使い方をすると、かえって格好のつかない、よくわからない曲・作品が出来上がってしまいます。
毎年毎年、自分が演奏して満足のいく曲、舞台映えする曲を作ってやろうと張り切っていた学生時代の私ですが、行き当たりばったりな作曲ばかりしていたので、たくさん失敗もしてきました。
今回は、実際に私がやってしまった失敗例を振り返ってみます。
1:ティンパニを置きすぎる

当時の私は、クラシック寄りの曲ばかり演奏していたので、必然的にオーケストラちっくな音色づかいでの作曲がほとんどでした。
電子オルガンはその名の通り、便利な電子楽器なので、実際のオーケストラの事情、各楽器の個性・性質をよく知らなくても、手軽にその音色を呼び出して、使うことができます。
なので、実際の楽器のことを知らない・配慮しないばっかりに、おかしなことが起きてしまいがちです。
とかく派手な曲、舞台映えする曲に憧れていた私にとって、足鍵盤でティンパニをドコドコ鳴らす瞬間は、最高に快感でした。
既成曲では、大事なところで一発、曲の最後のさいごに数発…。など、滅多に踏めないティンパニを、自分の曲の中でなら、好きなだけ使うことができるのです。
考えもなしに、ティンパニの大盤振る舞いをしました。
ちょっとでもフォルテ気味のところがあれば、ふんだんにティンパニを撒き散らしていくような様相だったかと思います。
しかし、オーケストラがずらっと並んだ舞台を思い浮かべてください。
ティンパニって並んでいても4個ぐらいですよね。
そしてティンパニが出せる音は、原則1個につき1音です。少なくとも、昔はそうだったみたいです。(なので、曲間などに手動で調律していたそうです。)
今では、ペダルを踏むと、にゅいーんと皮の張り具合が調節されるので、あんまり気にしなくても良さそうなものですが。(すみません、あまり詳しくないので『ティンパニって実のところはこういう事情だよ!』という情報があればぜひ教えてください。)
私の自作曲を実際のオケーストレーションで考えた時に、ティンパニが10も15もあるような、そんな状況を作り出してしまっていたのです。
意図して、音楽がより説得力を持ち魅力を放つために豪華絢爛にティンパニを多用しているのならともかく、ただの自己満足のための乱用だったので、これはいただけなかった失敗の一つですね。
今となっては、自己満足のためだけに音楽の流れを作ってしまうのも、それはそれで(突き抜けるものがあれば)ありなような気がしますが。
ましてや電子オルガンはそのためにあるような楽器ですよね。そのことにもう少し早く気付けていれば、また違った曲を作っていたのかもしれません。
2:実際の楽器の音域を気にしない(知らない)

生の楽器、とりわけ管楽器にはそれぞれ得意とする音域があります。そして鳴らすのが可能な音域があり、もちろん不可能な音域もあります。
ところが電子楽器は、そこのところ、おかまいなしに発音してしまうものですから、果たしてこの楽器はこの音が出せるのだろうかという感覚が薄れてしまいがちです。
音楽に触れる機会が増えてくると、感覚的に『この音は出ないなー』と何となく気付けるのですが、その経験が浅いと、やってしまいがちな失敗です。
低すぎるフルート、高すぎるホルン。(これは今だにやってしまいます。ホルンのきつい高音がとても好きです。)
ですが、体当たりでどんどん色んな楽器を鳴らして使い、いつか経験値がたまったそのときに、音域のことを気にしてあげられていたなら上出来だと思います。
3:実際の楽器の特性を知らない
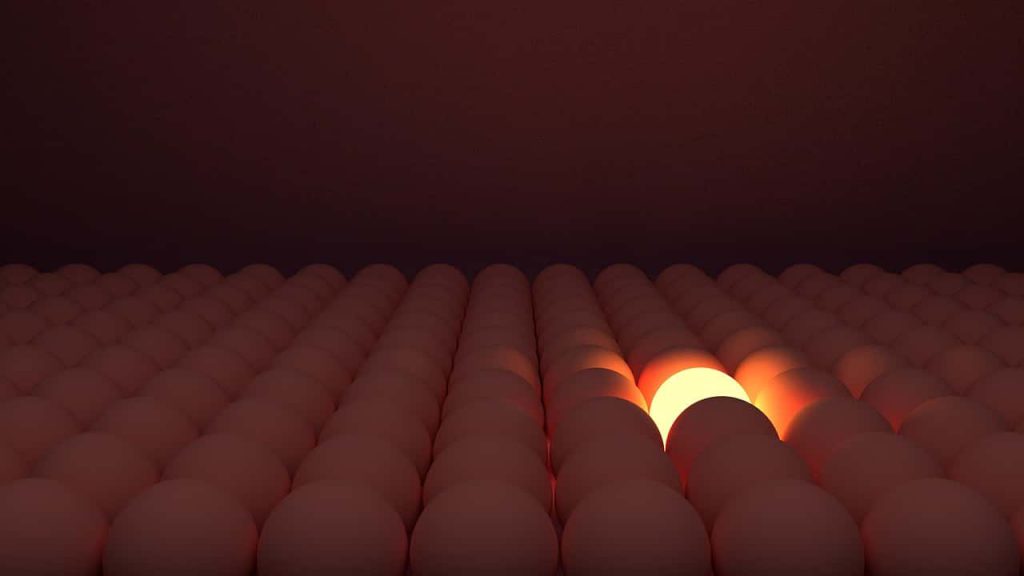
それは、即興演奏のレッスンを受けているときのことでした。(即興演奏といえば、リアルタイム作曲みたいなものです。こちらもやはりオーケストラ色の強い、クラシック寄りのやり方でいつもやっていました。)
曲の流れに変化をつけるため、ストリングスの音色からピチカートへ変えたのはいいものの、ピチカートをアルペジオで、(ハープのようにバラバラとさせた音符で)弾いてしまいました。
これはいただけません。
弦楽器の人たちは、普段は弓でこすりならしています。これを弓を使わず、指でぽんぽん弾くようにして鳴らす奏法が、ピチカートです。
これは、何十人もの人たちが、一音一音、息を飲むように合わせてでる音です。なので、一人の奏者が支配しているハープや鍵盤楽器とは全く事情が違うのです。
ピチカートがどうやって出ている音なのかということは分かっていましたが、実際の作曲・演奏においてそれを活かすことができなければ、知らないも同然です。
このように、鍵盤の形をした楽器から、菅や弦といった全く別の特徴をもつ楽器の音を鳴らす上では、気を遣った方がよいことが多々あります。
番外編:こんな工夫をしてみた

電子オルガンで、音色のことにばかり囚われて、ここは何の楽器かということまで同時進行で作曲をすることに疑問を持った年もありました。
なので、ある年の一曲は、ピアノで作曲をしてから、後付けで楽器・音色を考えていきました。
ところがこれはあまり良くなかったような印象があります。
作曲と音作り。これを同時にやらないと、かえって二度手間になってしまったのです。
時間が余計にかかるばかりでなく、『その楽器らしいフレーズ』というのも失われてしまいました。
電子オルガンで音色を考えながら作曲していると、『トランペットらしいファンファーレのような華やかなフレーズ』や、『木管楽器での波のような音列』など、具体的にオーケストレーションをイメージしながら曲を作ることができるのです。
歴史に名を遺すような大作曲家の方々は、ピアノ一台で素晴らしいオーケストレーションを考え出していました。ピアノすら使わず、頭の中で鳴らす音で間に合ってるようなすごい人もいました。
しかし、そういう人たちは、ものすごい天才なんだな、と思います。そして私はもちろん、ものすごい天才などではありません。
今はいい時代です。
ピアノの音のみ、頭の中の音のみを頼りに曲を作る必要なんてないのですから。
電子楽器、パソコンのDAW。いくらでも楽器の種類はあって、それを何人でも呼んできて、いかようにも目の前で鳴らすことが可能なのです。
しかも、それが少し頑張って貯める、ぐらいのお金で手に入れることができます。
ほんの少し前の時代では、この電子楽器やパソコンですら、大金持ちの娯楽みたいな値段だったと聞いています。
本当に、今はいい時代です。
まとめ

電子オルガンでオーケストラをやる。
これは、結局『予算削減』だとか、『まねっこ』に捉えられてしまいがちだと思っています。あるいは、一人で百人分もの音が出せる!といったマジックショーのようなすごさ、人目のひき方でしょうか。
いずれも、『電子オルガンが一つの楽器として目指すところではない』と、いつしか私はそう考えるようになりました。
なので一時期シンセサイザーのような『電子音』にばかり走ったりもしましたが、それでは結局シンセサイザーの『まねっこ』です。
電子オルガンというアイデンティティーを見つける旅路は、まだ始まったばかりのような気がします。
今のところの解答としては、こんな感じです。
多彩な音色を一人の人間の脳みそで支配、制御し、一つの音楽をリアルタイムで表現できる最高の楽器、それが電子オルガンでしょう。
そして、せっかくその楽器を使って作曲をするのですから、やはりどこまでも自由で、だけど強い意思を持った音楽を表現したいものです。
<最新の投稿>
- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう
- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16
- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15
- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14
- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13
<カテゴリー>
<タグ>
これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階

