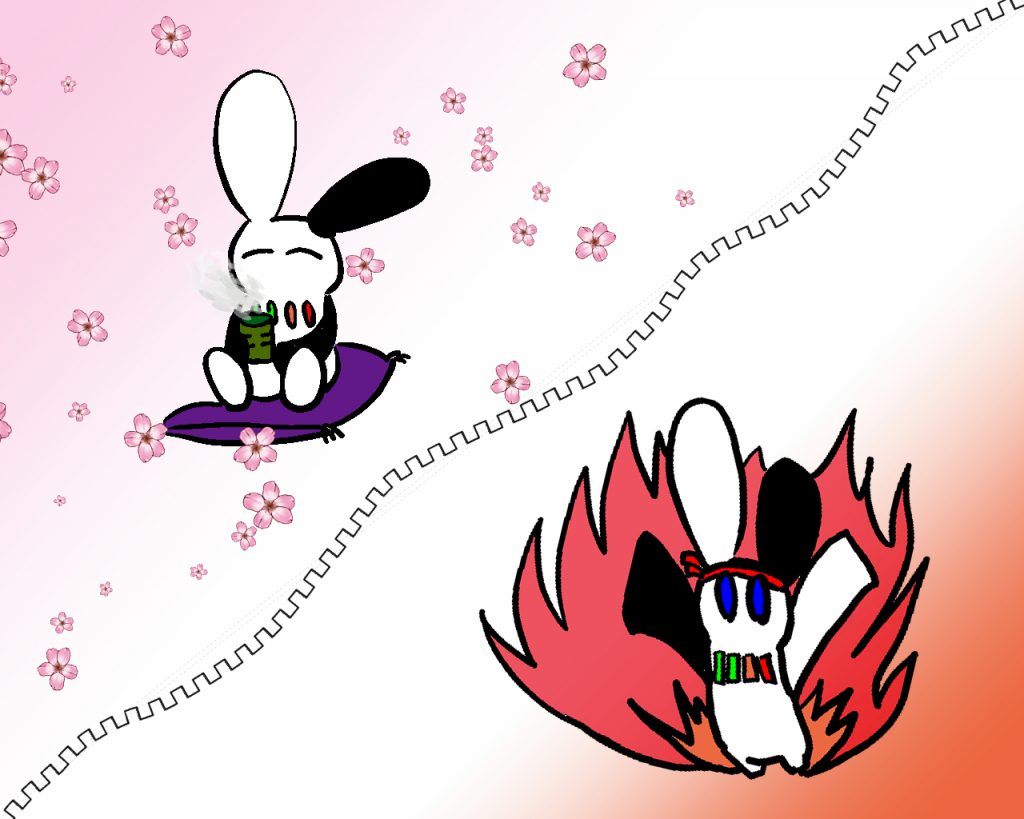たとえばデジタルに頼る
エレクトーンで育った私は、弾けない音符があっても、電子楽器の力でどうにかしてしまおうという思考にまず走ります。
その最たる例が「同音連打」です。
鍵盤楽器での同音連打は、非常にやりにくさを感じます。鍵盤楽器に限らず、何かを異常な速さで連打、連続させるというのは、あらゆるジャンルのパフォーマンスにおいて困難をともなうので、やる方は大変でも、見ている方としては楽しい見所なのかもしれませんね。
で、同音連打ですが、こんなものは、綺麗にディレイ(やまびこのような効果)をかけて、デジタルの力で演奏してしまえばいい、というふうに問題を解決してきました。
ディレイに助けてもらいながら同音連打をすると、どういうことが起きるかと言うと、1回弾くだけで、それが2回分になります。うまくディレイを操ることができたら、3回分にも4回分にもできます。つまり人間が演奏するのは半分ないしそれ以下の速さでよいということになるのです。これは楽ちんです。利用しない手はありません。
一方で、ピアノのような生楽器をメインに演奏している人は、自分の苦手な音符に直面すると、ひたすらストイックに、できるようになるまで練習していたりして、すごいなあと関心するばかりです。そうやって、自分のスキルをメキメキと高めていくことは、素晴らしいことです。私には決してできないことですので。
電子楽器の良さを活かしている、といえば聞こえはよいかもしれませんが、できないことから逃げていると捉える人もいるかもしれませんね。私は使えるものは使えばいいと思いますし、何よりそれが「音楽的」になっていれば万事OKだと思います。
たとえば、ディレイで同音連打を再現して、それが機械的でつまらない演奏になってしまっていたら、それは失敗です。電子楽器の悪いところが出てしまっています。一方で、電子の力を借りることによって小難しい作業から解放され、より入り込んだ表現に繋げられたのだとしたら、それはうまく電子楽器の利点を活かしていることになります。
このようにして、曲を演奏する際には、電子楽器らしい利点を活かしながら、自分の苦手なこと、やりたくない音符、できない表現を対処してきました。
みんなと自分に都合のよいオリジナル曲を作っちゃう
でも、そもそも自作曲ならばそのような問題は発生しないということに気がつきました。自分が弾きたい音符、演奏していて気持ちの良い表現のみを、ぎゅっと凝縮してしまえば、自分にとって理想的な曲が爆誕します。
しばらくはそのようにして、「自分が弾いていて心地よいもの」に執着していました。ところが、もう少し成長してくると、「弾き手だけでなく、聞き手の気持ちを考えなくては」という考えに至りました。(でも同音連打はしたくありません。笑)
この聞き手の気持ちというのが、ちょっとしたコツかもしれません。
自己中心的に作曲者が好きなものを並べ立てるのではなく、一定数の人たちが耳にした際の心地よさを想定して、曲を構成していくのです。
聞き手のことを意識し始めてからは、(それまではやたらと自己主張の強い曲が多かったのですが)「耳に優しい」であったり、「安心できる、予想のつく展開」や、いわゆる「わかりやすさ」が大切なんだなあという考えになりました。
しかし、ただただこの人畜無害な展開を続けていくばかりでは、人工知能に仕事を取られてしまうのがオチです。とてもシステマチックに完結できてしまいますから。
そこで、「聞いて心地よい」に加えて、「演奏して心地よい」がキーになってきます。
歌モノですと、わかりやすくいえば、「自分はこの曲をカラオケで歌いたいか…?」と自問自答しながら作曲しています。(私はもっぱら鍵盤しかできず、みずから歌入れはしないので、このような想定方法になります。)
カラオケで歌う際の気持ちよさといえば、
1 開放感のあるメロディー
2 言葉を発するだけで元気になる or 感傷に浸れるような歌詞
3 曲が進むにつれ気持ちが高まっていくような和音感
これらはあくまで個人の趣味ですが、私はこんなような曲だと、理想的であると感じるようです。
でも、世の中で好かれている曲にも、似たような傾向が多くあるということは、個人の趣味とみんなの趣味が重なる部分があるんじゃないかな?と信じています。ミュージカル系の楽曲に、そんなような傾向(上記3項目)が多くあるように見受けられますので…。
まとめ
『自分本位になりすぎず、でも自分の心地よいこと、自分の理想を中心に曲を作っていったら、それはみんなにとって幸せな曲になる』
ということです。少なくとも私は、このような考えになってからは、それまでの何倍も曲作りがラクになりました。
肩の力を抜いて、もっとよく見せようとか、そういうことは考えずに、自分の好きなものを、ちょっと相手を思いやりながら表現するのが、いろんな面で丁度良かったみたいです。
できない音符は無理をせず、得意な表現を伸ばした方が、演奏する方も、それを聞く方も幸せなはずです。
誰しも必ず、「こういう音符をやっているときが心地よいなあ」と感じるポイントがあるはずです。それは、その人の得意なところ、Goodなところなので、ぜひ伸ばしていきましょう。
できないことは、それなりに。
できることを、思い切り。
そんなふうにして、これからも音楽をやっていけたらいいなと思います。
<最新の投稿>
- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう
- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16
- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15
- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14
- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13
<カテゴリー>
<タグ>
これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階