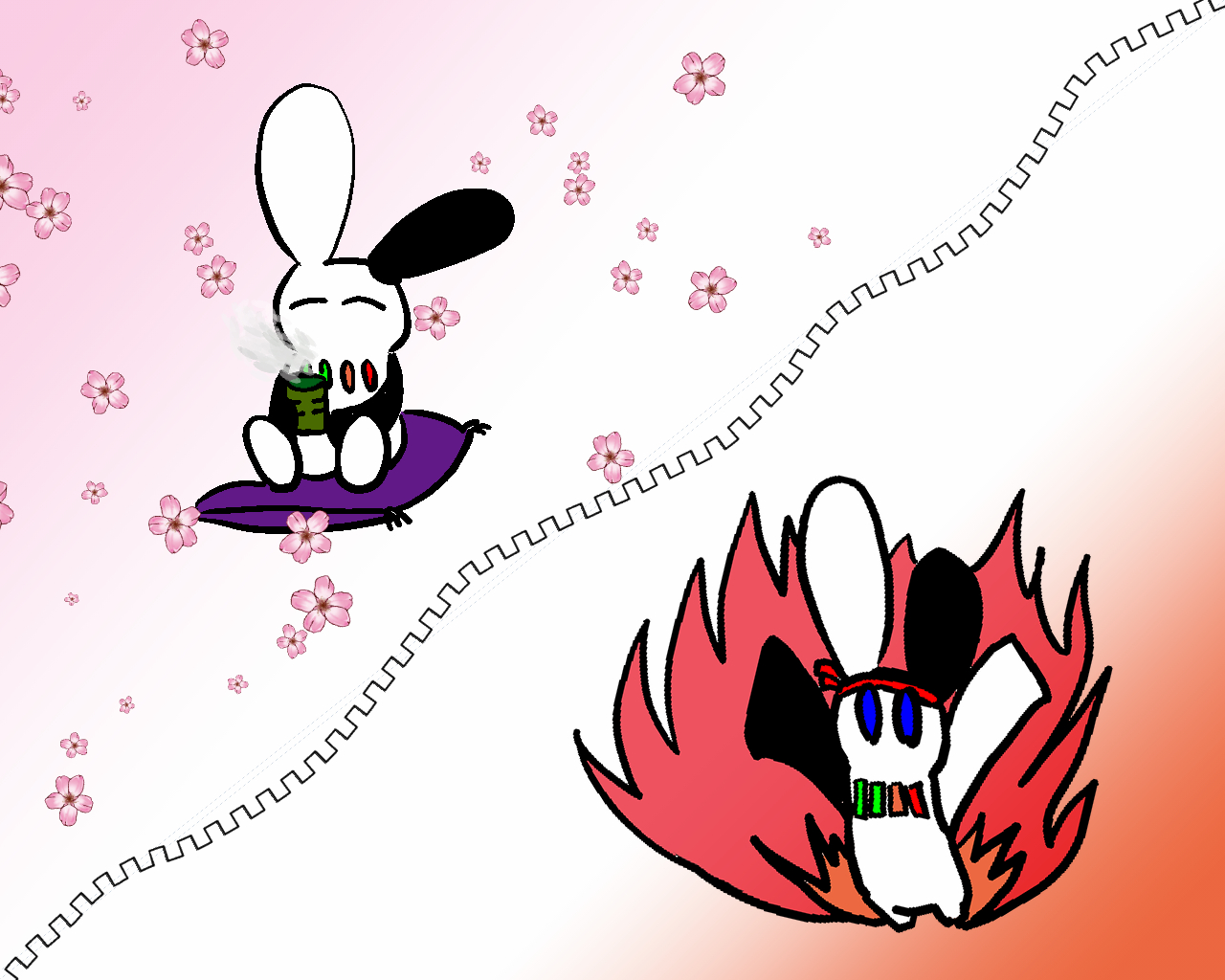
幼児期に通うヤマハの音楽教室では、歌を歌ったり、ごくごく簡単な曲をみんなで弾いたりするのですが、そのレッスンでは先生からこんなことをよく言われます。
『ここはやさしい感じで弾いてみよう』
『ここは元気よく歌ってね!』
長年ヤマハに通っていた自分にとっては、ヤマハあるあるのうちの一つです。
このあいだ、なんとはなしに旦那さんにその話をしたら、「そんな大事なことを教えてくれるのか」と言われて、なるほどなと思ってしまいました。
音楽をやる上で、コードがうんぬん、楽譜がうんぬんはさておいて、こういった「どんな気持ちで」ということは、とっても大事なことです。
子供に楽しく音楽をやってもらうにはどうしたらいいか、と考えたら、確かにこういった気持ちの部分を重点的に伝えていくことが大切に思えます。
大人になった今でも、音楽は気持ち一つでいかようにも変わってしまうものだと、常々思います。
言葉でさぐる
音は基本的に目に見えません。
機械を駆使して録音し、その波形を目視することは可能ですが、それはあくまで音の高低差や強弱が見えるだけです。
目に見えないからこそ、色々な言葉を使って音の様子を表現していくことが求められます。
その第一歩を示しているのが、このヤマハの先生の言葉なのでしょう。
「やさしい感じ」
と聞くと、思い浮かべるのは硬いより柔らかい、速いよりはゆっくり、シャキシャキよりはほっこり…。などなど。理解を深めていくと、どのように表現したら良いかがだいぶはっきりしてきます。
「元気な感じ」
だと、柔らかいよりは硬い。ゆっくりよりは速い。ほっこりよりはシャキシャキ。先ほどとは全て真逆の印象になります。
とどのつまり、この「やさしい」と「元気よく」さえマスターしてしまえば、音楽の表現はざっくりできているといっても過言ではありません。
もとをたどればたった2種類
人間の感情のスタートは、「快」か「不快」かの2種類だそうです。(その昔、途中で挫折した保育士免許取得の教科書にそう書いてありました。)
つまり、ざっくり2方向のことがわかれば、そこからどんどん枝分かれして、繊細なことがわかってくる、というふうに取れますね。
エレクトーンの落とし穴
さて。ここで一つ問題になってくるのが、エレクトーンを取り扱うがゆえの落とし穴です。
エレクトーンは、いろんな楽器の音色をいとも簡単に呼び出すことができます。
なので、音楽的な表現を、音色に頼りがちになってしまうことがあるのです。
例えば、フルートの音を選べば、何の気なしに弾いても、なんとなくやさしい表現になります。逆に、トランペットの音を選べば、元気な印象に引っ張られます。
このように、どんな楽器の音で演奏するのかは、音の印象に大きく繋がる要素の一つです。
ところがどっこい。それに100%頼ってしまうと、自分で表現することの意味が失われてしまいます。
全く同じフルートの音で、「やさしい」と「元気」の両方を表現するのが、音楽です。
これをすっぽり忘れたままエレクトーンの前に座るのは、ちょっともったいない気がします。
エレクトーンでの「表現力」
そこで!どんな楽器の音でも、「やさしい」と「元気」どちらの表現もできるようになれば、エレクトーンの利点を活かせると思いませんか?
せっかくエレクトーンとご縁があるのなら、他の楽器では身に付けられない表現力を身に付けたいものです。
金管でも木管でも。尖った音でも丸い音でも。
自分が思うがままの音色で、まずは「やさしい」と「元気」を表現してみましょう。そこからいろんな言葉に枝分かれさせていき、幅広い表現へと繋げていけば、今までとはまた一味違った音楽とのお付き合いができるのではないでしょうか。
<最新の投稿>
- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう
- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16
- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15
- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14
- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13
<カテゴリー>
<タグ>
これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階

