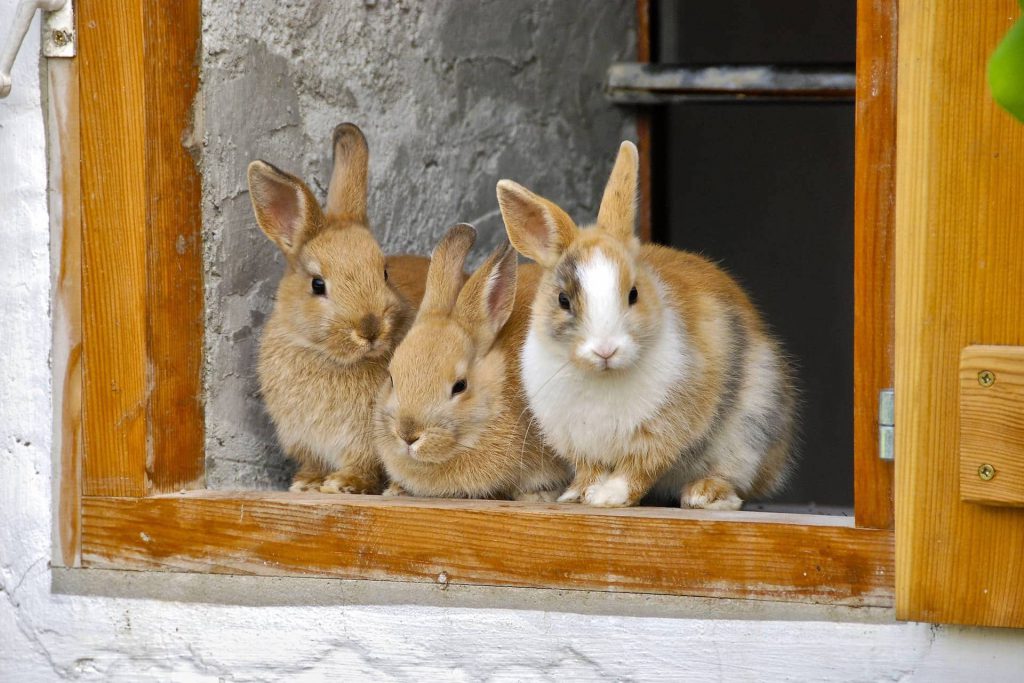楽器をやっている人たちの間には、『遊び弾き』という、とても大事な時間があります。これは、決まった曲を練習するでもなく、基礎練習であるハノンやスケールをやるでもなく、なんとなく楽器を鳴らして遊ぶ時間のことです。
合う合わないの個人差はありますが、実はこの『遊び弾き』という行為が、楽器と仲良くなるとてもいい方法の一つなのです。
さあ、鍵盤の前にいざ座ってみてください。何を弾いても誰も聴かないし、誰もあなたに関心を示さないような環境があれば、なおいいです。そして、心のおもむくままに、音を鳴らしてみてください。
頭に浮かんだCMソングを弾いてみるもよし。
メリーさんの羊を弾いてみてもよし。
指が動くままに楽譜にできないような音の連続を楽しむのもよし。
しかし何をしても良いとなると、かえって困ってしまうのが人の常です。夏休みの自由研究のように、ある程度例を示されたところで、何をすればいいのか決めかねて、結局腰は重いまま、時間だけが過ぎていきます。
そこで、どんな遊び方があるか、その一部をご紹介します。
知っている曲を耳コピーしてみる
これは先ほどにも出てきました。一番やってて楽しい、しかも良質な練習になる遊び弾きです。
好きな歌、耳にこびりつくCMソング、テレビから流れるメロディー、なんでも構いません。耳コピーなんていうと、ハードルが高いように感じてしまいますが、そんなことはありません。気楽にやるのが一番です。
まず、一音いち音正確を記す必要はありません。なぜなら楽譜にする訳ではないし、音程だってリズムだって適当で『これが近いかな?』くらいでいいのです。
そして、ある程度濃く記憶に残っている曲なり一節なりの方がいいです。いちいちCDを部屋から探して引っ張り出して、それを再生する。またはYouTubeで検索しているうちに、やる気がなくなってしまうことになりかねません。遊び弾きは、そんなにがんばる必要がないものです。
見出しでは、知っている曲というふうに表記しましたが、どんなに細かいパーツでも構わないのです。メロディーだけ、ベースラインだけ取ってみる。曲に一瞬出てくる素敵なひとフレーズだけ弾いてみる。これも立派な耳コピーです。
簡単なフレーズ・メロディー・曲を全調に移調して弾く
よく耳にするハノンやスケール。
ハノンは、一つの基本的な音形を、下から上に、上から下に、リフトのように両手で平行移動させて、指の動きをよくするものです。
スケールは、各調の音階をやはり下から上に、上から下にと行ったり来たりさせるものです。何調はこの指遣いで、何調はこんな響きで動いて、という感覚を身につける練習法です。
この二つは、鍵盤楽器を選択した人なら必ずと言っていいほどまず最初に課される課題の一つです。
これらの練習法も、確かに鍵盤の基礎的な感覚を身につける上で欠かせない、大切な練習法としてこれまで大切にされてきました。しかし実際、ハノン・スケールを地道に毎日積み重ねていくのは、あまり楽しい作業であるとはいえません。ましてや、幼い子供が好き好んで取りかかれるような練習ではないことは確かです。
このハノン・スケールと同じような要素が、もっと楽しく・自由に得られる、画期的な練習方法があります。それがこの、移調奏です。
元の調から別の調へ移動させて演奏することを移調奏と言います。これをどんな順序でも構わないので、ひたすらやって、すべての調を制覇しましょう。アトラクションを巡っているような感覚で楽しめますし、しかも鍵盤がもっともっと得意になれます。
そしてここでも前項と同じくポイントがあります。なるべく簡単なメロディーからはじめてみましょう。いきなり動かしづらいメロディーだったり、長い曲だったりすると、なかなか思うように指が動かず、嫌になってしまいます。
最初は特に簡単で、短いものから取りかかってみましょう。片手ずつやるのも、簡略化してメロディーとベースラインだけにして移調していくのも、効果的です。
それでは、ここでどんな風にして全調を巡る移調奏をしたら楽しいか、その一例をご紹介します。
おすすめの全調巡り方1:半音ずつ
オーソドックスなやり方としては、半音ずつ上げていくやり方があります。
♯、♭なしのハ長調からはじまり、いきなり♭5つの変ニ長調へ突入する。そしてまた穏やかな♯2つのニ長調へ行き、再び主音が黒鍵である♭3つの変ホ長調へ。この白鍵はじまりと黒鍵はじまりとが交互にやってくることにより、難易度に緩急の波がつけられて、変化のある練習が楽しめます。
♯5つのロ長調という最後の関門をくぐり抜け、またハ長調へと舞い戻った時、あなたは間違いなく数分前のあなたより、鍵盤が上手になっています。
長調だけでなく、短調も忘れずトライしてみましょう。
おすすめの全調巡り方2:完全4度ずつ
調の関連性、つながりをより感じるのに有効的なやり方が、完全4度ずつ上げていくやり方です。
ハ長調からへ長調、へ長調から変ロ長調、変ホ、変イ、変ニ長調…。まで到達すると、今度は嬰へ長調からロ長調、ホ、イ、ニ、ト長調まで回ったらまたハ長調に戻ってきます。
そうです。この巡り方では、行きには♭が一つずつ増えて、帰りには♯が一つずつ減っていくという現象が起きます。そしてこれらの移調はすべて、曲の最後に1度セブン(次の調における5度セブン)をくっつけると、スムーズになります。
例えば最初の移調でいくと、ハ長調の1度セブン(へ長調の5度セブン)にあたるコードはC7です。これをうまいこと曲のおわりに接続すると、次の調であるへ長調に自然な移動が可能になります。
この順路では、♭、♯の数がやまなりに増減する楽しみがあるほか、調と調が近い関係どうしで繋がっていくので、各調の親戚関係が感覚的に理解できます。
【移調奏のポイント】
指が少し動きにくかったな、という苦手な調は、何回かループしてみても、良い練習になります。でもそれも嫌にならない程度に。ほどほどにしましょう。 風のように駆け抜けるもよし。とどまって苦手潰しをするもよし、です。
思いのままに鍵盤を鳴らしてみる
これはもう、発散のための独り言のようなものです。
まずは、手をパーなりグーなり、好きなように形をつくって、好きなような強さで、好きなような場所を叩いてみてください。好きなようなリズムでもって、それを連続させてもいいでしょう。
どこをどう弾こうと、(多少前衛的な響きという感じは否めませんが)必ず案外アリな響きがします。
そうです。鍵盤は、何をやってもアリなんです。やってはいけないことなんて、何もありません。
こんなふうに、衝動的で、偶発的な音を、感情のまま波のように創り出していく。これも立派な即興演奏なんです。
また、そんな即興演奏に多少の統一感、秩序をもたせたいときは、一つ簡単なルールを決めます。それは、基本的に白鍵のみで弾くことです。
ハ長調は、♯、♭が一つもない調。つまり、白鍵だけ弾いている限り、どこまでいってもハ長調になります。この鍵盤の特性を活かして、楽に1つの調にとどまって演奏することができます。(イ短調も同じく♯、♭ゼロの調ですが、音階の下りの際に♯が一つ必要だったり、そうでなかったりするので、ハ長調だと思って弾く方が、楽かと思います。)
その逆、黒鍵だけで弾くのも、さらに視覚的にわかりやすく、統一感のある音階の中で演奏することができます。
『ねこふんじゃった』を弾ける人がたくさんいるのは、この特性を活かした調での演奏が広まったから、というのが有力なセンだと思っています。
あの『ねこふんじゃった』は、実は嬰ヘ長調で演奏されています。シャープの数はなんと6こです。しかしこれだけ多くの人に愛され、演奏されているのは、(導音である『ミ♯』いち音を除いた全ての音が)黒鍵のみでの演奏法だったからでしょう。もしもこれがハ長調だったら、『ねこふんじゃった』に、これほどの人気はなかったかもしれません。
白鍵だけ、黒鍵だけに絞って弾くことで、どんなに直感的に演奏をしても、多少まとまりのある、理性のある音がなってくれます。
遊び弾きに正解はない
遊び弾きのやり方は、人によって、楽器によって、さまざまです。
ぜひ、自分が今やって一番楽しいもの、やりたいものをやってみてください。
鍵盤楽器、音楽には、やってはいけないことなんて一つもありません。何をやってもいいんです。
遊び弾きを通して、鍵盤楽器とさらに仲良くなりましょう。
<最新の投稿>
- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう
- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16
- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15
- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14
- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13
<カテゴリー>
<タグ>
これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階