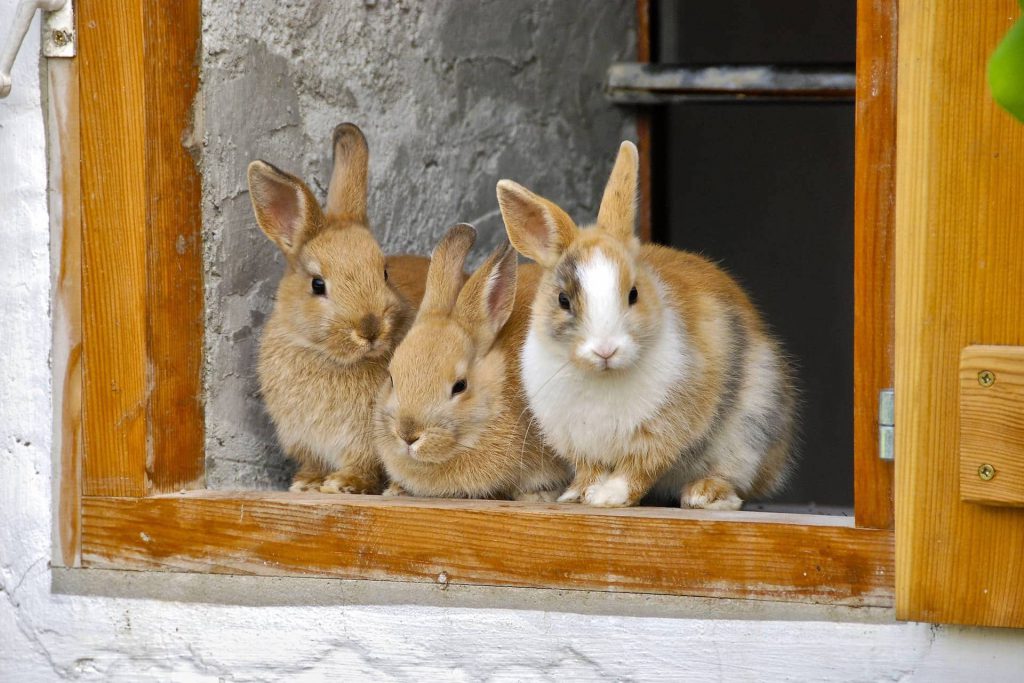初見演奏。これは、楽器の中でも特に鍵盤楽器奏者についてまわる、必要不可欠なスキルです。
つまりは、初めて見る楽譜を『リアルタイムで』読みながら、同時に演奏していくという芸当です。
これが得意になれば、かなり充実した音楽生活を過ごせること間違いなしです。
初見演奏が得意になるということは、楽譜を読むスピードが格段に速くなるということを意味します。そして、楽譜を読むスピードが速いということは、それだけ多くの曲と速いスパンで出会えるということです。
弾きたい曲が、あっという間にとりあえずの形で弾けるようになる。このことは、楽しく練習を進める上で、大きな助けになります。
それに、音楽の仲間同士で、その場でやりたい曲をすぐに試すことができます。あるいは、鍵盤楽器奏者は伴奏者としてその音楽力を求められる場面が多々あるので、そんなときに一番必要になるのがこの初見演奏ということになります。
私の経験からすると、初見演奏が得意になれば、もうかなり怖いものは少なくなっていました。そんな初見演奏を、苦手から得意にシフトするには、何をすれば良いのかを考えてみました。
しかしながら、これはもう、数をこなして慣れてくるのを待つしか、上達のしようがないスキルなのではないかという結論に、今のところ至っている次第です。
その『数のこなし方』は千差万別。どんなやり方でこの初見演奏を得意にしていくかは、人によって向き不向きがあるかと思います。
なので今回は、実際に私がやって来たことの中で、『おそらくこれが初見演奏上達に役立った』という練習の方法を紹介します。
一つ目:曲集

『既成曲の楽譜で、なるべく簡単でリズム・音色が楽しいものをたくさん初見で弾く』というのが、まず一人の練習の際にいちばん役に立った方法です。
楽に譜読みができて、わりとすぐ最後まで弾けて達成感が得られる曲だということがポイントです。
電子オルガンの曲集では、リズムデータ・音色がセットで売られていることが多いです。
このリズムデータというのがみそで、ほぼ初見の状態でリズムをかけながら演奏することにより、インテンポから置いて行かれないように必死で楽譜を読む練習になります。
ただし、あんまりにも弾けない状態のままリズムをかけてもイライラしてしまうばかりなので、要注意です。
そうならないためには、実際のグレード試験などでもそうですが、予見をするのがよいでしょう。
鍵盤に触れる前に、ざっと楽譜を最後まで見て、少し読みにくいところ・読むのに時間がかかるところをあらかじめ読んでおきます。今までで抑え慣れていない和音などが多くこれにあたります。
慣れないうちは、初めから難易度を下げて、メロディーだけで。和音とベースだけで。など分けて練習するのも有効です。
二つ目:人前

『初めて見る楽譜を、人前で演奏する。』
先ほどは一人の練習の場合ですが、協力を頼める人が近くにいたら、これは一つ目を大いに上回る効果を示す練習方法です。
ここで大事なのは、聴いてもらう相手が家族や友人だからといって、間違えながら止まりどまりの演奏をしてはいけない、ということです。それでは初見演奏の練習にはなりません。
なるべく正確に譜面を読み、さらにはそれを『演奏』にまで持っていかなくてはならないので、これはかなりエネルギーを使う練習です。
もちろん、そのぶんの効果も見込めるということになります。
三つ目:伴奏

これが、私の人生で最も効果的だった初見演奏の練習方法になります。
歌や楽器の『伴奏』を、その場で渡された楽譜でこなしていきます。
誰かと一緒に演奏するぶん、緊張感は一つ目、二つ目の比ではありません。
絶対にテンポから外れてはいけないし、コードなど弾く内容も正確でなければならないので、初見演奏の練習にはもってこいです。
このとき、どんな楽譜を目の前にしても、楽譜の全てを完璧に弾けるほどのスキルが備わっていればそれで申し分ないのですが、それはとても難しいことです。
なので、ある程度削ぎ落として良い情報を瞬時に判断して、大事な音符だけは絶対に逃さないように演奏する技術も同時に身につきます。
この技術は、アカデミックな試験の場面では望ましくないかもしれませんが、そうではないほぼ全ての場面でとても役に立ちます。
まとめ

個人的には、『初見演奏』というと、どうしてもおカタく聞こえてしまうのであまりよくないと思います。
つまりは、『ぱっと見て、ぱっと弾ける』という技術のことです。
その場で・ざっくり弾けて、それが棒立ちの音楽でなく、ちゃんと流れていく生きた音楽、つまり『演奏』になるように。
これが得意になると、その後の音楽との付き合い方がガラッと変わるかもしれません。
<最新の投稿>
- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう
- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16
- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15
- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14
- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13
<カテゴリー>
<タグ>
これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階